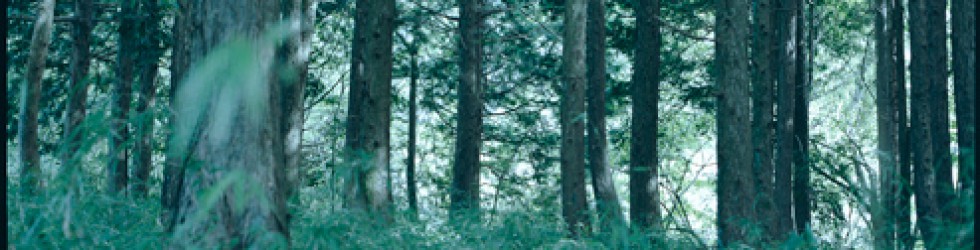歴史資料から見る西川材 その1
2015/09/30
植林
西川地域で林業、特に植林事業が始められたのは江戸中期以降と考えられています。
林業地全域での植林、育成、出荷までの大規模な林業生産が行われるようになったのは、明治以降と考えて良さそうです。
本格的な林業地としての西川地方を世に売り出したのは、植林し撫育ー伐採ー運材ー流通というサイクルに乗せた育成林業開始以降のことでしょう。
18世紀半ばの江戸市場における西川材の市場価値を認識し、それの拡大生産に着目した林業家が植林を奨励し、先駆的な林業家がそれを試みる。
それまでの自然林の伐採からは得られなかった利益の循環を図ることが出来るようになったのです。
また、このことは自然生態系を壊すことなく、自然の循環系にも良い結果をもたらしたとも言えます。
西川地方の全体像
この地域の森林面積はおよそ2万ヘクタールです。
昭和29年発行の森林組合の記録によると、「森林面積約21000町歩(約20826ヘクタール)、蓄積は約691万石(約1246287.6立方メートル)となっています。
昭和54年に同じように作成された「西川林業」(埼玉県農林部林務課編)には「森林面積は20637ヘクタール、蓄積は390万立方メートル」となっています。
樹種に関しての記載もありますが、それはまた別の機会に・・・
昭和29年と昭和54年を比較してみると、木材の蓄積量がわずか25年の間に倍増しています。
太平洋戦争中軍需用として材木が大量伐採されて、西川地方でも大径材は船舶用、小径材も宿舎用等に使用することから、計画生産を無視した伐木が行われて、戦後の山林は荒廃しました。
そこで、「総合農林業開発振興計画」を策定して、大規模な植林を奨めました。
従来は薪炭用としていた雑木山も伐採し、杉・桧の苗を植林して将来の経済を計画的に豊かにしようというものでした。
昭和29年は、この計画の実施段階で、その結果が昭和54年の蓄積量の増加ということになります。
関連記事
-

-
西川材とは?
西川材と呼ばれる材木 埼玉県飯能市、日高市周辺は古来から良質の木材を産出してきま …
-

-
歴史資料から見る西川材 その2
歴史資料から見る西川材 その1 へ 林業前の西川地域の産業 西川林業地の中心であ …
- PREV
- 西川材とは?
- NEXT
- 歴史資料から見る西川材 その2